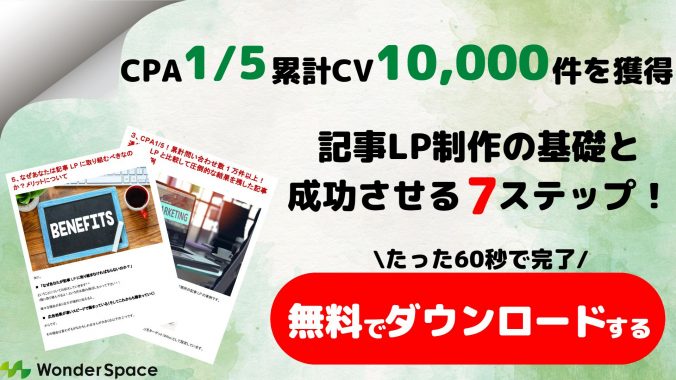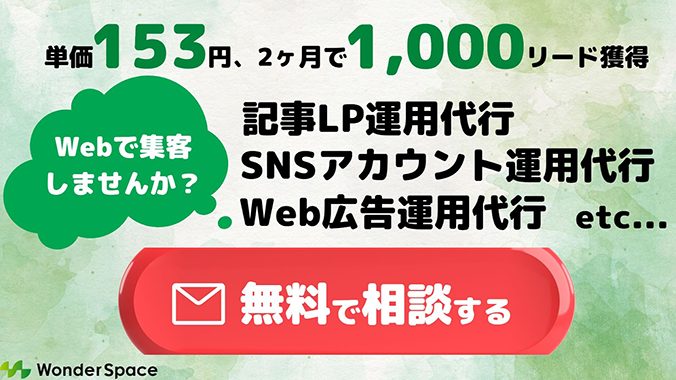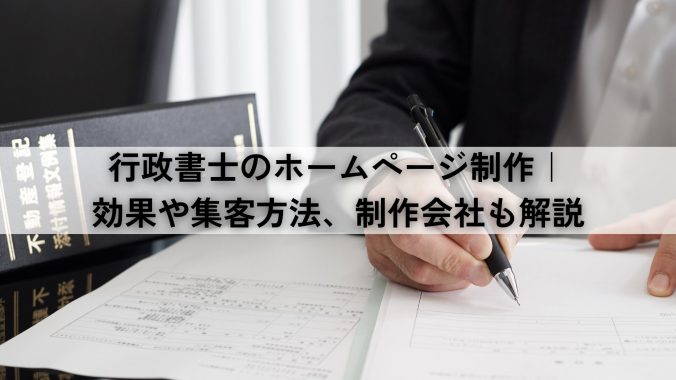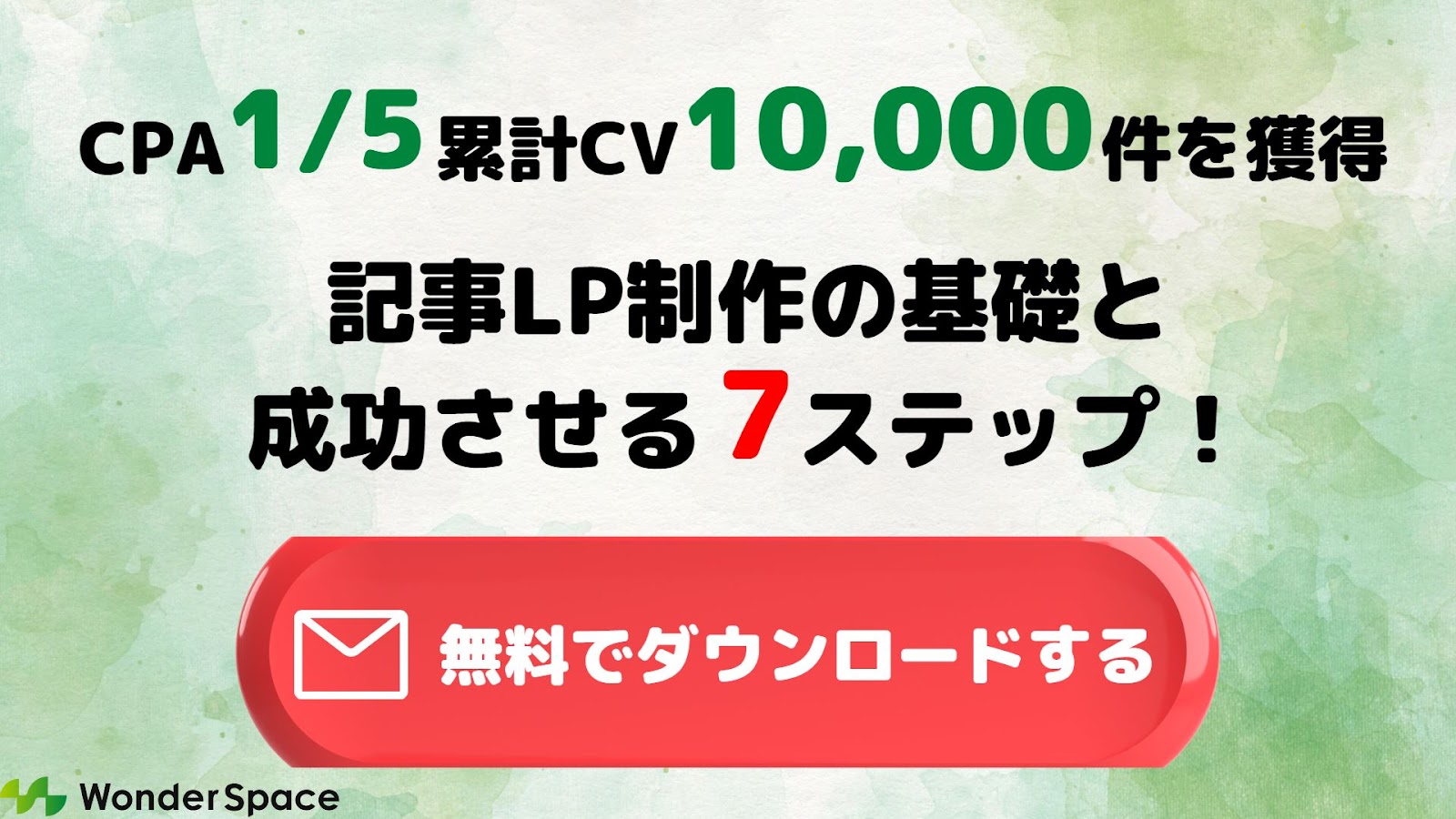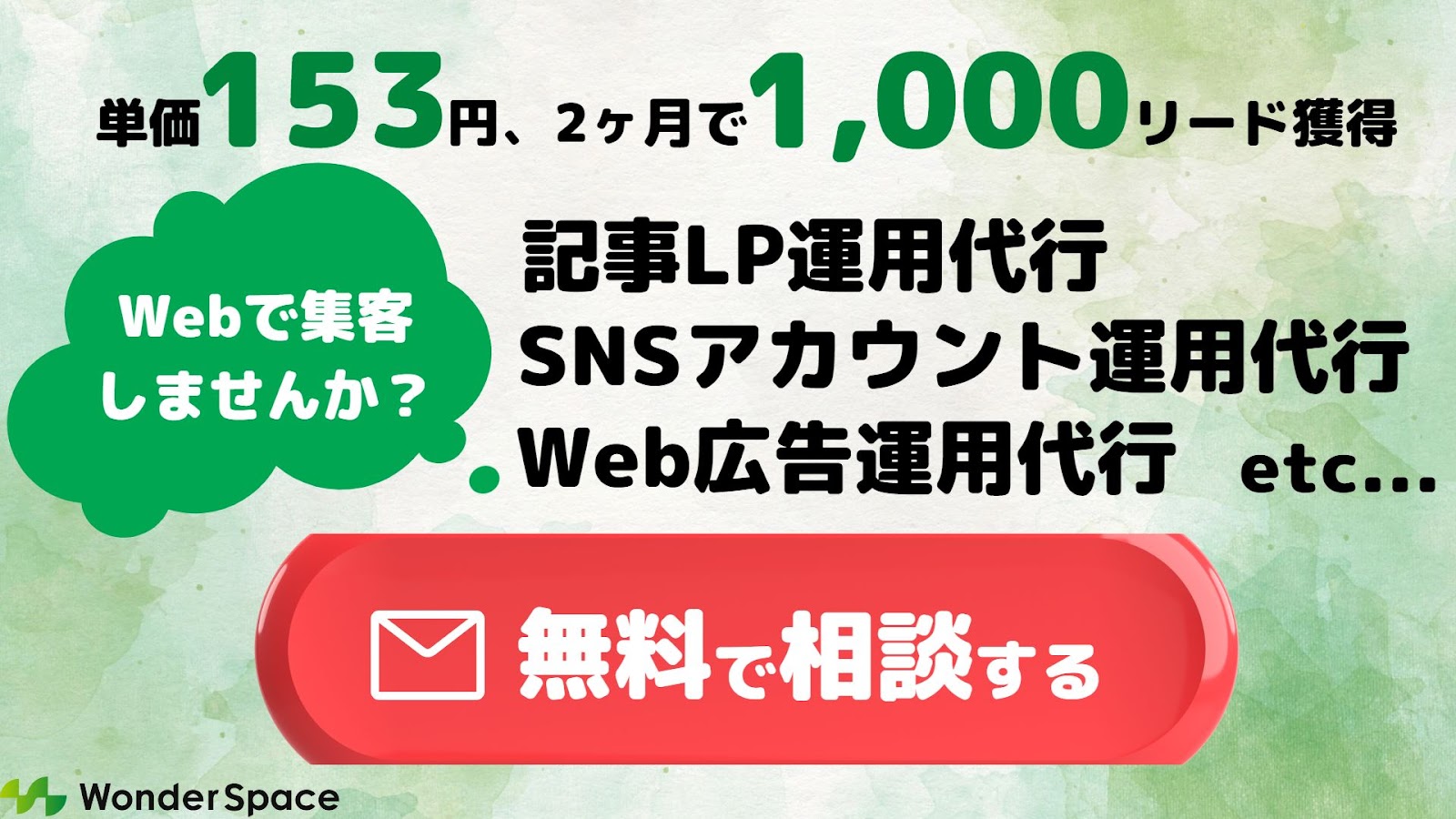インフィード広告とは?配信するメリットから成功事例まで徹底解説
記事LP
2023.6.27 (更新日:2023.6.27)

インフィード広告がデジタルマーケティングの世界で急速に注目を集めていますが、その具体的な内容や効果を詳しく理解している方は、なかなかいないのではないでしょうか?
そこで、今回は、以下の2点を詳しく解説します。
・インフィード広告の基本とその活用法
・成功事例
記事LPの作り方を知りたい方は、以下の記事LP完全ガイドブックを無料ダウンロードして、ご覧ください!
1、インフィード広告とは

インフィード広告とは、その名前が示す通り、ユーザーがフィード(情報の流れ)をスクロールしている途中に自然に表示される広告のことを指します。
この広告形式は、特にSNSやニュースアプリなどのタイムライン上でよく見られます。
例えば、あなたがFacebookをスクロールしているとき、友人の投稿やお気に入りのページの更新情報の間に、自然に広告が表示されることがあります。
その広告がまさにインフィード広告です。
この広告は、他の投稿と同じようにフィードの一部として表示されるため、ユーザーにとっては自然な閲覧体験を提供します。
また、インフィード広告は、ユーザーが関心を持つ可能性のある内容に基づいて配信されるため、一般的なバナー広告よりもユーザーの関心を引きやすいとされています。
例えば、あなたが最近キャンプ用品について検索したとすると、Facebookのフィード上でキャンプ用品のインフィード広告が表示される可能性があります。
このように、インフィード広告は、ユーザーの自然な情報閲覧の流れの中に広告を巧みに組み込むことで、ユーザーの関心を引き、効果的な広告効果を発揮します。
(1)インフィード広告とネイティブ広告の違い
インフィード広告とネイティブ広告は、しばしば混同されがちですが、両者は異なる概念です。
インフィード広告は、WebサイトやTwitter、FacebookなどのSNS上にコンテンツを掲載する形式で出稿する広告です。
各媒体に適したデザインで広告を出稿できるため、良い意味で“広告色が薄い”のが特徴といえます。
一方、ネイティブ広告は、広告が出稿される媒体のコンテンツと同じ形式やスタイルで表示される広告を指します。
そのため、インフィード広告はネイティブ広告の一種とも言えますが、すべてのネイティブ広告がインフィード広告とは限りません。
(2)インフィード広告の市場規模とその成長
近年、インフィード広告の市場規模は拡大し続けています。
サイバーエージェントによる2017年の調査結果によれば、2017年には昨年比約4割増となる約1,903億円に到達し、2023年にはさらに約3,921億円規模に成長すると予測されています。
(参照:サイバーエージェント)
Webプロモーションやアプリプロモーションの領域においても、インフィード広告の出稿金額は増加傾向にあります。
これは、インフィード広告が従来型のプロモーション方法と比較しても費用対効果の高い施策であると捉えられるからです。
(3)インフィード広告を配信できる主要な媒体
インフィード広告を出稿できる主な媒体としては、「Facebook」「Instagram」「Twitter」「TikTok」「LINE」などのSNSのほか、「Yahoo!プロモーション広告」「Google広告」などのメジャーな検索エンジンもあります。
以下に、各SNSの特徴とその利点を説明します。
1.FacebookとInstagram
ユーザー情報が登録されているため、設計したペルソナに近い層に配信がしやすい。
Facebookは30〜50代のユーザーが多く、ビジネスシーンでの利用が多い。
Instagramは20〜30代のユーザーが多く、静止画だけでなく動画でのアピールが可能。
2.TikTok
10〜20代のユーザーが多い。
短い動画を中心としたコンテンツが特徴で、ユーザーを飽きさせない仕組み作りで成功している。
3.LINE
アクティブユーザー比率が高いためアクションにつながりやすい。
年齢層も幅広く、あらゆる層にアプローチできる。
4.Twitter
「バズる」ことで広告の拡散が期待できる。
20〜30代のユーザーが多いが、40代以上にも利用者が伸びている。
Yahoo!広告やGoogle広告は、それぞれYahoo!検索やGoogle検索を利用するユーザーに対して広告を配信することができます。
これらの広告は、ユーザーが検索結果を見ている間に、自然にフィード(情報の流れ)の中に広告を表示することができます。
例えば、あなたがGoogleで「旅行」を検索したとします。
検索結果の上部や下部に表示される広告はGoogle広告(具体的にはGoogle検索広告)の一部です。
これらの広告は、ユーザーが検索したキーワードに関連する商品やサービスを提供する企業から配信されます。
2、インフィード広告のメリットとデメリット

(1)インフィード広告のメリット
①ユーザー体験への配慮
インフィード広告の最大のメリットの一つは、ユーザー体験への配慮にあります。
これは、インフィード広告がユーザーの自然な情報の流れ、つまり「フィード」に組み込まれるため、ユーザーにとって違和感のない形で広告が表示されるという特性から来ています。
例えば、あなたがSNSのタイムラインをスクロールしているとき、友人の投稿や気になるニュース記事の間に突如として大きなバナー広告が表示されたらどうでしょう?
それはおそらく、あなたの情報の流れを乱し、違和感を感じるでしょう。
しかし、インフィード広告ならば、その広告はあなたのタイムラインの一部として自然に溶け込み、情報の流れを乱すことなくあなたの目に触れることができます。
このように、インフィード広告はユーザーの情報の流れを尊重し、ユーザー体験を妨げることなく広告を表示することが可能です。
これは、ユーザーが広告を無視する傾向が強い現代において、非常に重要な特性と言えるでしょう。
また、インフィード広告はその表示形式がテキストや画像、動画など多様であるため、広告主は自社の商品やサービスを最適な形でユーザーに伝えることができます。
これにより、ユーザーは自然な形で広告を受け入れ、広告主のメッセージを理解することが可能となります。
②視認性の高さ
インフィード広告の視認性の高さは、その配置によるものです。
ユーザーが情報を探しやすい「フィード」の中に表示されるため、視認性が高いと言えます。
これを理解するために、ある日常生活のシーンを想像してみてください。
あなたがスーパーマーケットで買い物をしているとき、目の高さにある商品は下の棚にある商品よりも見つけやすいでしょう。
同様に、ウェブサイトでもユーザーの目に触れやすい位置に広告があると、その広告はより効果的になります。
③広範なターゲット層へのアプローチ
インフィード広告は新規リードの獲得にも適していると言われています。
自社商材に馴染みがないユーザーでも、自然に広告が表示されるため、興味を引きやすいです。
また、SNSや検索エンジンなど、多様な媒体で配信できるため、広範なターゲット層にアプローチすることが可能です。
(2)インフィード広告のデメリット
①クリエイティブの難しさ
インフィード広告のクリエイティブ制作は、一般的なバナー広告やテキスト広告とは異なる特殊なスキルを要求します。
その理由を以下に詳しく説明します。
1.ユーザー体験の一部としての広告
インフィード広告は、ユーザーが自然に目を通すコンテンツの一部として表示されます。これは、広告がユーザーの体験を中断するのではなく、それを補完するように設計されていることを意味します。
このため、広告はユーザーが自然に受け入れられる形で、かつ興味を引く内容でなければなりません。
2.ユーザーの期待に応える
インフィード広告は、ユーザーがコンテンツを読んでいる最中に表示されるため、その広告が提供する情報や体験は、ユーザーがその時点で求めているものと一致していなければなりません。
これは、広告の内容がユーザーの期待に応え、その興味を引くものでなければならないということです。
3.広告の認識
インフィード広告は、一見すると通常のコンテンツと区別がつかないように設計されていることが多いです。
しかし、広告であることを明確に示さないと、ユーザーは「騙された」と感じる可能性があります。
そのため、広告であることを適切に表示しつつ、ユーザーの興味を引くバランスを取る必要があります。
②誤クリックの可能性
インフィード広告は、ユーザーのフィードに自然に溶け込むため、ユーザーが広告であることに気づかずにクリックしてしまう「誤クリック」が発生する可能性があります。
これは、広告主にとっては無駄な広告費を消費する結果となります。
3、インフィード広告の費用体系

インフィード広告の費用体系は主に以下の3つに分けられます。
(1)クリック課金型
クリック課金型は、広告をクリックしたユーザーに対して課金される形式です。
広告がクリックされなければ課金されないため、広告主にとってはリスクが少ないと言えます。
ただし、先述の通り誤クリックが発生する可能性があるため、その点は注意が必要です。
(2)インプレッション課金型
インプレッション課金型は、広告が表示された回数に対して課金される形式です。
広告が表示されるだけで課金されるため、広告主にとってはリスクが高いと言えます。
しかし、広告の露出を確実に増やしたい場合には有効な手段となります。
(3)エンゲージメント課金型
エンゲージメント課金型は、広告に対するユーザーの反応(いいね、コメント、シェアなど)に対して課金される形式です。
ユーザーが広告に対して何らかのアクションを起こした場合にのみ課金されるため、広告主にとってはリスクが低いと言えます。
ただし、ユーザーがアクションを起こすまでには、広告のクオリティが求められます。
4、インフィード広告で成果を出すための戦略

(1)ターゲティングの明確化と誤クリックの防止
インフィード広告の効果を最大化するためには、まずターゲティングを明確にすることが重要です。
具体的なターゲット層を設定し、その層に合わせた広告を配信することで、広告のクリック率やコンバージョン率を向上させることが可能です。
また、誤クリックを防ぐためには、広告のデザインや配置に工夫が必要です。
広告がユーザーのフィードに自然に溶け込む一方で、広告であることを明示することで、誤クリックを防ぐことができます。
(2)クリエイティブの工夫とテスト運用
インフィード広告のクリエイティブは、ユーザーの注目を引きつつ、広告であることを適度に示す必要があります。
そのため、クリエイティブのデザインやメッセージには工夫が求められます。
また、どのようなクリエイティブが効果的であるかは、ターゲット層や媒体により異なります。
そのため、複数のクリエイティブを作成し、テスト運用を行うことで、最も効果的なクリエイティブを見つけ出すことが可能です。
(3)ランディングページの質の向上
広告をクリックしたユーザーが最終的にコンバージョン(購入、問い合わせなど)に至るためには、ランディングページの質が重要となります。
ランディングページは、広告のメッセージを補完し、ユーザーをコンバージョンに導く役割を果たします。
そのため、ランディングページは広告のメッセージと一致する内容であること、ユーザーが求める情報を提供すること、ユーザーが求めるアクションを取りやすい設計であることが求められます。
さらに、ランディングページの前に記事ランディングページを挟むことによってコンバージョンまで導くことができます。
記事ランディングページについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
「記事LPとは?作り方から実際に成果を出すためのコツを徹底解説」
(4)フリークエンシーの設定と広告デザインの工夫
広告のフリークエンシー(同一ユーザーに対する広告の表示回数)を適切に設定することも、インフィード広告の効果を最大化するための重要な戦略です。
フリークエンシーが高すぎると、ユーザーにとって広告がうっとうしく感じられ、広告の効果が逆に下がる可能性があります。
逆に、フリークエンシーが低すぎると、広告の存在をユーザーが認識できない可能性があります。
また、広告デザインの工夫も重要です。
特に、広告の見出しや画像は、ユーザーの注目を引くための重要な要素です。
見出しは、ユーザーの興味を引くような内容であること、画像は、ユーザーの目を引くようなビジュアルであることが求められます。
5、インフィード広告の成功事例とその分析

(1)株式会社SQUIZの例

こちらは、Instagramが媒体のインフィード広告です。
(参考:Oops HAIR)
こちらのインフィード広告では、薄毛の型をターゲットにしてAGA治療が紹介されています。
InstagramやFacebookでは、ユーザー情報が登録されているため、設計したペルソナに近い層に配信がしやすい特徴があるのです。
そのため、こちらのインフィード広告は、ユーザー情報を絞ることが可能なInstagramで配信することによってターゲットに刺さるコンテンツを作成できたと考えられます。
(2)BizHintの例

こちらは、Sponichi Annexが媒体のインフィード広告です。
(参考:BizHint)
こちらのインフィード広告では、社長と社員との関わりについて紹介されています。
周りのコンテンツとの見た目の差をなくすことで広告色を薄くしつつも、「世界一給料が高い」というタイトルで惹きを誘うことで、ターゲットに刺さるコンテンツを作成できたと考えられます。
成果を出せる記事LPの作り方の完全フォーマットを無料で公開
記事LPの作り方のポイントや大まかな流れは、理解できたでしょうか?
あなたが、いざ実際に記事LPを制作することになった時にこの記事を参考にするのも良いと思います。
しかし、記事LPを実際に作ろうとしてみても「結局、何から手を付けていいのかわからない」「考えるのが難しい」と思いませんか?
記事だけを参考にして、いざ記事LPを作ってみたら誰でも作れるようなレベルの記事LPが完成してしまったり、、、
今回は、こういった悩みを解決してきた弊社が、記事LP制作で最初から最後まで何をすればよいのかをまとめてあるフォーマットを、「記事LP完全ガイドブック」として無料で公開します。
「記事LP完全ガイドブック」を見ながら記事LPを作るだけで効果的な記事LPを制作できるようになるので、ぜひダウンロードしてみてください。
記事LP制作は、難しいからこそしっかりとしたフォーマットが必要です。
成果の出る記事LPには、決まって効果的な記事LP制作のフォーマットがあります。
ぜひ、こちらをダウンロードをして、記事LPで成果を出してください!
6、まとめ
インフィード広告は、その自然な配信形式と高い視認性から、デジタルマーケティングの中でも注目されている広告手法です。
しかし、その効果を最大化するためには、ターゲティングの明確化、クリエイティブの工夫、ランディングページの質の向上など、様々な戦略が求められます。
また、インフィード広告の費用体系は、クリック課金型、インプレッション課金型、エンゲージメント課金型の3つが主流となっています。これらの費用体系を理解し、自社の目的や予算に合わせて適切な費用体系を選択することも、インフィード広告の成功に繋がります。
本記事では、インフィード広告の基本的な知識から、成功事例までを詳細に解説しました。
これらの情報を参考に、ぜひインフィード広告の活用を検討してみてください。