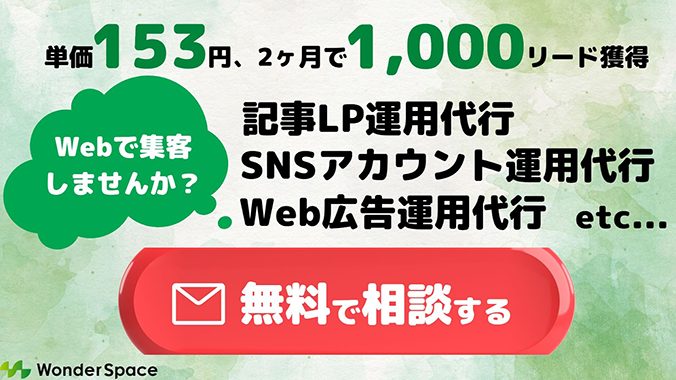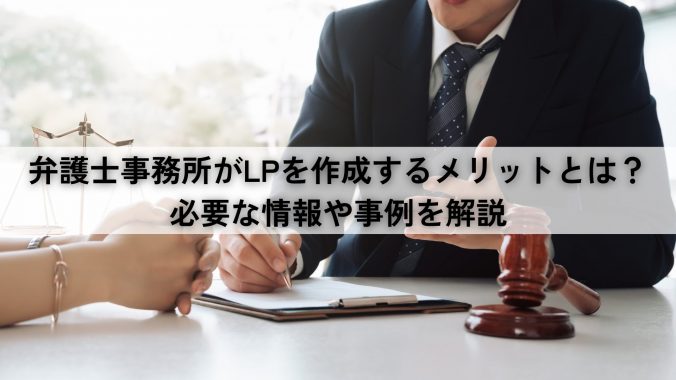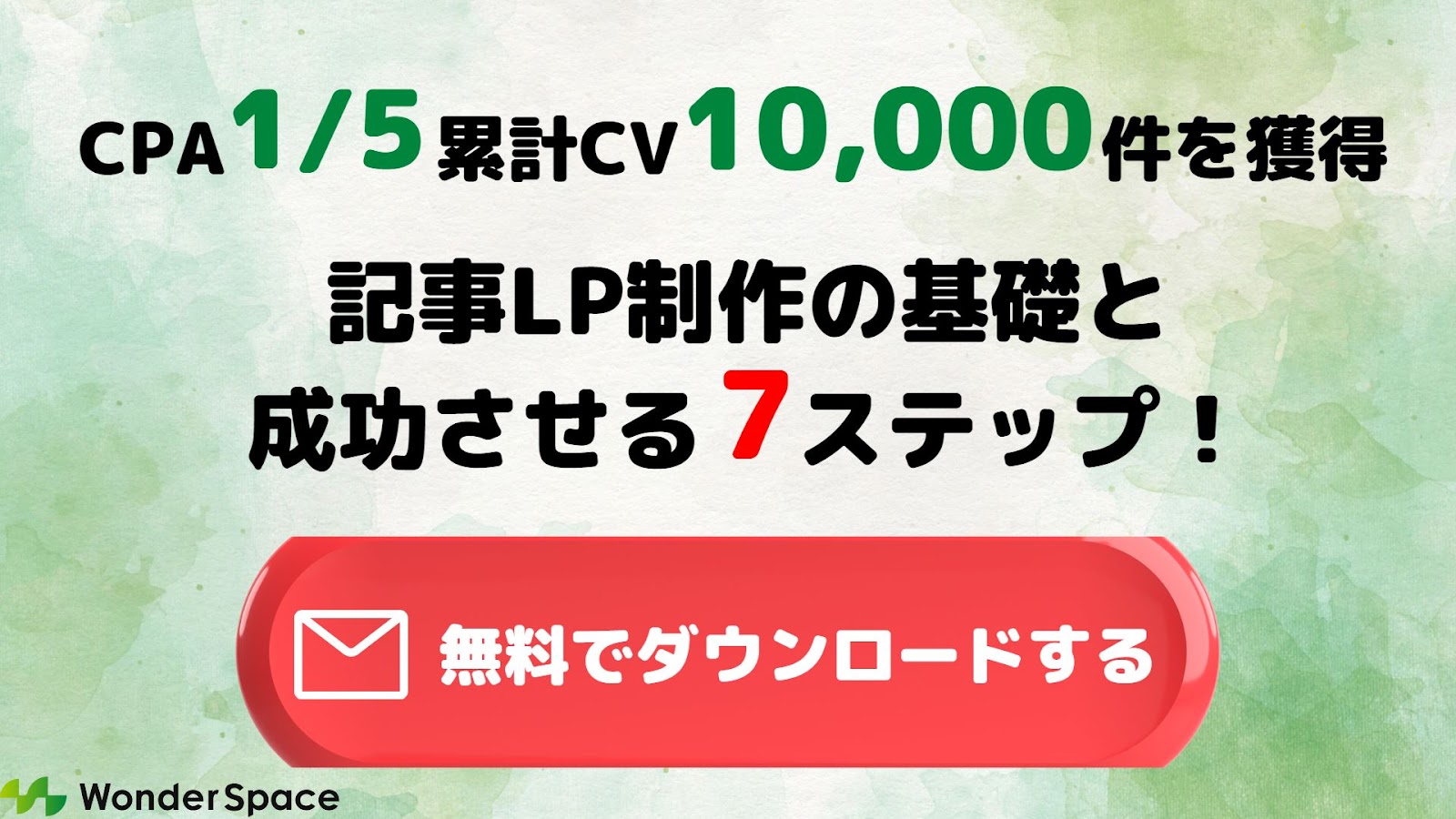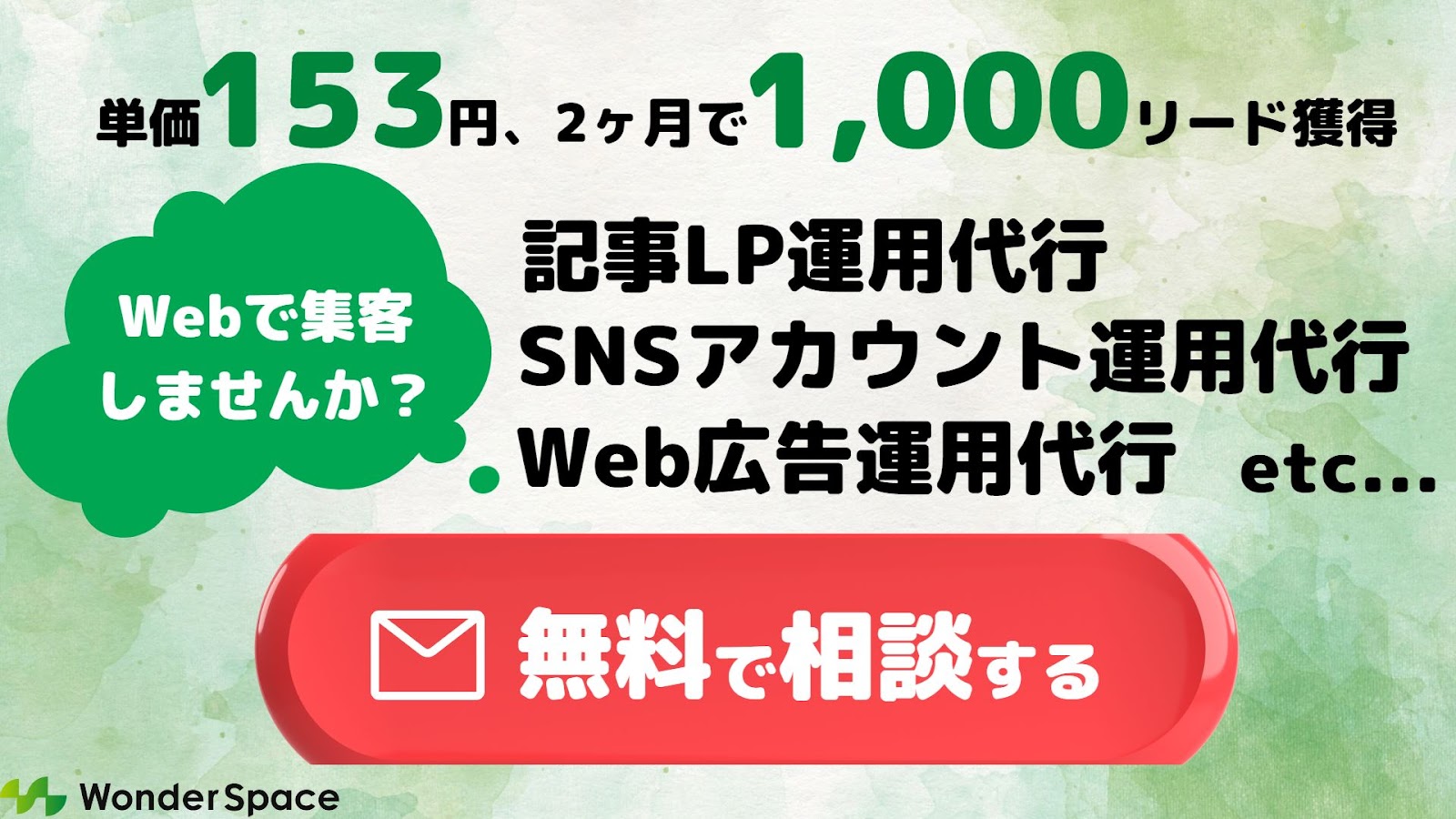記事LPとは?作り方から成果を出すための5つのコツを徹底解説
記事LP
2023.6.27 (更新日:2023.8.23)

『記事LP』は、ユーザーが抱えている悩みに寄り添うことに重きを置く特徴があります。
さらに、記事LPは広告感が薄いため読んでもらいやすいので、CV(コンバージョン)の決定に直結させることができます。
記事LPとよく聞くものの、「記事LPって何?」「結局、何から始めたらいいのかわからない」「自分じゃできないのでは?」と思った方に向けて、記事LPの作り方から成果がでるコツまで解説します!
この記事では、以下の2つを徹底解説します。
・記事LPについて
・記事LPの作り方について
皆さんのご参考になれば幸いです。
記事LPの書き方を知りたい方は、以下の記事LP完全ガイドブックを無料ダウンロードして、ご覧ください!
1、記事LPとは

記事LPとは、webメディア風のランディングページ(LP)のことです。
記事風の構成にすることによって広告色を抑え、ユーザーの興味・関心を惹きつけるという特徴があります。
今までは、広告からLPに遷移させる方法が主流でした。
しかし、最近では、読み進めてもらいやすさの観点から、記事LPに遷移させる手法が注目されています。
(1)記事LPとLPとの違い
記事LPとLPとの違いは、ユーザーへのアピール方法です。
LPは、企業側がアピールしたい内容を前面に押し出す特徴があります。
それに対して、記事LPは、ユーザーが抱えている悩みに寄り添うことに重きを置く特徴があります。
このように、商品やサービスを利用してもらうという目的は同じですが、ユーザーへのアピール方法が異なります。
(2)記事LP作成のメリット
記事LP作成のメリットは、以下の4つです。
・広告感が薄いため読んでもらいやすい
・ユーザーの比較検討プロセスを省ける
・LPに遷移する前に購買意欲を高められる
・ユーザーに刺さる訴求ポイントを生み出せる
メリットを理解することで、ユーザーに刺さる記事LP作成ができるようになります。
以下に1つずつ詳しく解説します。
①広告色が薄いため読んでもらいやすい
記事LPのメリットは、いい意味で広告色が薄いことです。
記事LPは、商品やサービスのアピールを説明するよりも、ユーザーの悩みや問題に寄り添うことが重要視されます。
そのため、ユーザーは記事LPに対して、広告色が薄いと感じやすくなります。
②ユーザーの比較検討プロセスを省ける
記事LPのメリットは、ユーザーの比較検討プロセスを省けることです。
多くのユーザーは、ひとつの商品を購入するまでにさまざまな情報を調べます。
具体的には、以下の4つのプロセスによって情報を調べます。
1.商品について興味を持つ
2.サービス内容や得られるメリットを調べる
3.他の商品よりも魅力的なものかどうかを比較する
4.本当に、自分に必要な商品かどうかを判断する
記事LPはこれらの情報を全て盛り込めるため、ユーザーの比較検討プロセスを省かせることができます。
そのため、CV(コンバージョン)に直結させることができるのです。
③LPに遷移する前に購買意欲を高められる
記事LPのメリットは、潜在ユーザーへアプローチでき、顕在ユーザーへと育成することができることです。
潜在ユーザーは、解決したい課題を持っているが、商品やサービスの存在を知らないユーザーです。
記事LPでは、潜在ユーザーに対して、気づきを与えることで購買意欲を高めます。
そして、顕在ユーザーへと育成した上で、LPに遷移させることができるのです。
そのため、結果的にCVR(コンバージョン率)が高まります。
④ユーザーに刺さる訴求ポイントを生み出せる
記事LPのメリットは、ユーザーに刺さる訴求ポイントを生み出しやすいことです。
記事LPは、ユーザーと同じ目線で、ユーザーニーズを想定して作成されます。
ユーザーの悩みや、問題に対して徹底的に深堀るため、訴求内容のズレを抑えることができるのです。
記事LPのメリットについて、詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
「記事LPのメリットを紹介|7つのメリットと唯一あるデメリットとは 」
(3)成功した記事LPの導入事例
弊社における成功した記事LPの導入事例を以下に2つ紹介します。
こちらの記事LPでは、B型肝炎の給付金が貰える人の解説や、どれくらいの金額がもらえるのか、またその手続き等を紹介しています。
こちらの記事LPでは、給与が増えない現状や、将来を見据えた時の副業の重要性、その中でも不動産投資に注力すべき理由等を紹介しています。
記事LPの導入事例を詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
「記事LPの成功事例を紹介|参考になる成功事例と5つの型を紹介」
2、記事LPの作り方

記事LPは、3つの流れに沿って作成されます。
以下の3つの流れをテンプレートとしてお使いください。
・記事LP作成のための事前準備をする
・記事LPの見出しを作成する
・記事LPを実際に書く
それぞれ、詳しく解説します。
(1)記事LP作成のための事前準備をする
事前準備では、「ユーザーが抱える問題」「ユーザーが回避したいデメリット」「ユーザーが成功する未来」を明確にします。
事前準備をすることで、よりユーザーの心を掴む言葉を生み出すことができるようになるのです。
①ユーザーが抱える問題
ユーザーの抱える問題は、以下の3種類です。
外的問題:置かれている環境に影響を受ける問題
内的問題:精神的に抱えている問題
哲学的問題:何に悩んでいるのかわからない問題
特に記事LPでは、内的問題にアプローチすることが非常に得意です。
ユーザーが抱えている問題に対して、適切な解決策を与えてあげることによってユーザーに行動喚起させます。
内的問題を深堀るためにも、ユーザーが抱える問題の種類を理解して、ユーザーの悩みを明確にしましょう。
そうすることで、ユーザーから愛される商品・サービスとなり、熱狂的なユーザーが生まれます。
企業側が映画のようにストーリー制を持った「ユーザーが直面するであろう問題」について語ることで
ユーザーは、その企業が提供する商品やサービスに興味を持つようになります。
②ユーザーが回避したいデメリット
ユーザーが回避したいデメリットを、明確に示してあげることによって、より商品やサービスに興味をしめすようになります。
特にユーザーが得られるメリットと、失うデメリットのギャップを大きくすればするほど興味を引くことができます。
そのためには、デメリットを詳しく記載してあげることが必要です。
例えば、交通事故のデメリットの例を挙げます。
「交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に依頼しなければ治療を打ち切られてしまう可能性があります。たとえ、完治していない状態でも打ち切られてしまう可能性があるのです!」
このように、どんな危機にさらされているかをしっかり定義することで、ユーザーの心をより引き付けられる文章を作成できます。
そのため、必ずユーザーが商品やサービスを使わないことで、どんなデメリットがあり何を失ってしまうのかを明確にしましょう。
③ユーザーが成功する未来
ユーザーが成功する未来を明確にしてあげましょう。
具体的には、商品やサービスを利用することで、ユーザーにどんな未来が訪れるのかを明確にします。
上記②のデメリットと同様に、詳しく記載してあげることが必要です。
そうすることで、ユーザーの心の中にある「何かを変えたい」という思いにアプローチでき、商品やサービスに興味をもってもらいやすくなります。
(2)記事LPの構成を作成する
事前準備が完了したら、以下の4つの流れで記事LPの構成を作成します。
・ペルソナを設定する
・ユーザーへのアプローチ方法を決定する
・悩みを解決する情報をまとめて見出しにする
・見出しの流れがスムーズかどうか確認する
①ペルソナを設定する
ペルソナとは、商品やサービスの典型的なユーザー像のことです。
ペルソナ設定では、細かいターゲティングをした方がターゲットの心に刺さりやすくなります。
年齢や性別だけでなく、居住地や職業、年収、家族構成といった細かいターゲット設定を行いましょう。
ペルソナを作成することで、個人の悩みに沿ったアピールをすることができ訴求力が強まります。
実際に、こちらのベリーベスト法律相談所の記事LPの例を紹介します。
「50万円〜3600万円!肝臓に病を抱えるあなたが国からもらえるかもしれない給付金とは?」
こちらの記事LPでは、ペルソナ設定を以下の設定で作成した結果、CV数が5倍になりました。
「B型肝炎ウイルスに感染している人でまだ給付金の受け取り手続きをしていない人」
悩みを具体化させたペルソナを設定することが、重要です。
②ユーザーへのアプローチ方法を決定する
記事LP作成では、ユーザーへのアプローチ方法を決定します。
そのために、以下の項目を徹底的にリサーチしましょう。
・ユーザーの思い込み
・ユーザーの欲求
・ユーザーの感情
上記3点をリサーチすることで、訴求力の強い記事LPを作成することができます。
ユーザーの潜在的ニーズに商品やサービスの特徴を重ねて記事LPに反映させましょう。
また、ユーザーの関心レベル別でアプローチ方法が異なります。
ユーザーの関心レベルは、以下の3つです。
・潜在ニーズレベル
顧客自身も気づいていない、明確化されていない状態。
・準顕在ニーズレベル
ニーズはあるが、商品やサービスを知らない状態。
・顕在ニーズレベル
顧客自身が、欲しいものやサービスを自覚している状態。
上記3点のユーザーの関心レベルの違いによって、ユーザーへのアプローチ方法が異なります。
例えば、B型肝炎ウイルスに感染している人向けの記事LPタイトルは、以下の通りです。
潜在ニーズレベル:「B型肝炎ウイルスの感染を防ぐために知っておくべき感染経路」
準顕在ニーズレベル:「インターフェロンによる肝炎治療を受ける前に知っておくべき10のこと」
顕在ニーズレベル:「テノゼットの効果や助成金の受け取り方」
このように、ユーザーの関心レベルの違いによって、ユーザーへのアプローチ方法が異なるのです。
③悩みを解決する情報をまとめて見出しにする
見出しタイトルには、見出し内に記載されている内容を一言で表す一文を入れます。
なぜなら、読者は必ずしも記事のすべての文章を読んでくれるとは限らないからです。
さらに、ペルソナが抱えている悩みを解決するために、必要な情報を記入します。
下記項目をテンプレートとしてお使いください。
・効果
・期間・時間
・やり方・やること・使い方
・価格(割引などのお得感)
・実績(データ、口コミなど)
・権威性(有名な推薦者やメディアが取り上げているなど)
・緊急性・限定性
・専門性
・意外性・好奇心
上記項目を基に、見出しを作成することで、離脱率の低下に繋がります。
特に、「自社製品を使えばどのような悩みが解決するのか」という点を見出しタイトルに含めると良いでしょう。
④見出しの流れがスムーズかどうか確認する
最後に、作成した見出しの流れがスムーズかどうか、確認してください。
特に、ユーザーの悩みに対して適切に解決策が提示されている構成かどうかについて確認します。
具体的な解決策が提示されることで、ユーザーの行動喚起に繋がるのです。
(3)記事LPを実際に書く
記事LPの構成が完成したら、実際に記事LPのライティングをします。
ユーザーの悩みに寄り添った上で原因と改善策を具体的に分かりやすく記載することが重要です。
その際の、効果的なライティングのポイントは次の5つです。
・画像や太字を活用する
・ユーザーのメリットを押し出す
・文脈に合わせて導線を設置する
・タイトルや見出しを工夫する
・5文字以上の漢字が続かないようにする
①画像や太字を活用する
読みやすい記事LPにするために、適宜画像や図を挿入します。
フローや関係図など、言葉よりも図にしたほうが伝わりやすい内容は図にしてみましょう。
また、必要に応じて画像を入れることで、文章の内容を具体的にイメージしやすくなり、読みやすい記事になります。
さらに、重要な項目は太字や赤字を使い目立たせることで、読みやすい記事になるのです。
②ユーザーのメリットを押し出す
商品をアピールする情報よりもユーザーに有益な情報をメインに記事LPを作成します。
商品のアピールが強いと、ユーザーは押し売りをされているような感覚になり、離脱するリスクが高まるのです。
③文脈に合わせて導線を設置する
導線は、複数個所に設置する方が効果的です。
文脈に合わせずに、「〇〇を購入してください」といった導線を設置してしまうと、ユーザーは違和感を抱いてしまいます。
そのため、「〇〇について詳細を確認する」などの文言に変えたり、文脈に合わせて導線を設置したりするなどの工夫をしましょう。
④タイトルや見出しを工夫する
内容が充実したコンテンツを作成しても、タイトルや見出しが魅力的なものでなければ、読まれないというケースは少なくありません。
以下の内容を参考に、タイトルや見出しを工夫しましょう。
(ⅰ)具体的な数字を入れる
タイトルに具体的な数字を入れることで、ユーザーの関心を高めることができます。
例えば、「在宅で月収5万円を稼げる副業まとめ」「起業家の99%が知らない成功の秘訣とは」です。
また、数字を入れるときは偶数ではなく奇数にしてみてください。
統計によると、数字を奇数にした方がクリック率は20%ほど上がることが分かっています。
(ⅱ)疑問系で終わらせる
疑問系で終わらせると、タイトルのクリック率が高まります。
例えば、「格安スマホって大丈夫?大手キャリアとの違いを解説」「サブスクっていいことばかり?メリットとデメリットを紹介」です。
タイトルを疑問系にすることで「記事を読めば答えが分かる」という心理にさせることができるため、結果的にクリック率が高まるのです。
(ⅲ)記号を活用しながら2つのフレーズに分ける
記号(!、?、|、「」など)を活用することで、タイトルや見出しの内容が頭に入りやすくなります。
例えば、以下の通りです。
訂正前:刑事事件の示談で人生を台無しにしないために知っておくべきこと
訂正後:刑事事件の示談|人生を台無しにしないために知るべき5つのこと
このように、タイトルや見出しの内容が頭に入りやすくなり、ユーザーの関心を高めることができるのです。
(ⅳ)5文字以上の漢字が続かないようにする
漢字が連続してしまうと読みづらい印象を与えてしまいます。
ひらがなやカタカナを挟むなどして漢字が連続しないように注意してみてください。
5文字以上の漢字が連続したら文章やタイトルを見直しましょう。
3、記事LPで成果を出すための5つのコツ

記事LPで成果を出すためには、5つのコツを抑えておくことが大切です。
(1)事前準備でユーザーニーズを明確にすること
ユーザーのレビューや口コミをチェックすることで、より具体的なニーズを把握できます。
一例ではありますが、以下に挙げたツールを活用してみるといいでしょう。
・Yahoo!知恵袋
・Googleサジェスト
・amazonや楽天などのレビュー
(2)記事LP内に統計データなどの根拠を載せること
「〇〇と言われています。」と記載するだけではなく、統計データを用いるなどして根拠も一緒に載せましょう。
信憑性の高い情報と認識され、ユーザーからの信頼度が上がります。
(3)アイキャッチ画像にこだわること
見出しや文章だけでなく、アイキャッチ画像にこだわることで反応率を上げることができます。
特に、下記のことに注意してみてください。
・目を惹く画像にすること
・記事の内容に関連している画像にすること
・カラーを決めたり文字を入れるなどして、独自性を出すこと
(4)記事LPのリンク先をLPにすること
記事LPは、ユーザーに共感するコンテンツを作成し行動喚起させることが最大の目的です。
何より記事LPでは、商品やサービスに関する情報が少ないため、購入・利用させるところまで導くのは難しいでしょう。
記事LPを挟み、商品やサービスの魅力をアピールすれば、LPでは満たせなかったユーザーの「購入したい」という意欲を上げることができるのです。
(5)CV数最大化のために記事LPの改善を繰り返すこと
一回でCVR(コンバージョン率)の高い記事LPができるとは限りません。
反応がよくなかった場合は、ブラッシュアップをして改善を繰り返してみてください。
改善を続けていくことで、自然と反応のいい記事LPが作成できるようになります。
成果を出せる記事LPの作り方の完全フォーマットを無料で公開
記事LPの作り方のポイントや大まかな流れは、理解できたでしょうか?
あなたが、いざ実際に記事LPを制作することになった時にこの記事を参考にするのも良いと思います。
しかし、記事LPを実際に作ろうとしてみても「結局、何から手を付けていいのかわからない」「考えるのが難しい」と思いませんか?
記事だけを参考にして、いざ記事LPを作ってみたら誰でも作れるようなレベルの記事LPが完成してしまったり、、、
今回は、こういった悩みを解決してきた弊社が、記事LP制作で最初から最後まで何をすればよいのかをまとめてあるフォーマットを、「記事LP完全ガイドブック」として無料で公開します。
「記事LP完全ガイドブック」を見ながら記事LPを作るだけで効果的な記事LPを制作できるようになるので、ぜひダウンロードしてみてください。
記事LP制作は、難しいからこそしっかりとしたフォーマットが必要です。
成果の出る記事LPには、決まって効果的な記事LP制作のフォーマットがあります。
ぜひ、こちらをダウンロードをして、記事LPで成果を出してください!
4、まとめ
いかがでしたでしょうか?
記事LPは、ユーザーに共感するコンテンツを作成し、行動喚起させることが最大の目的です。
一回でCVR(コンバージョン率)の高い記事ができるとは限らないので試行錯誤を繰り返して改善していきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
記事LPの作り方を知りたい方は、記事LP完全ガイドブックを無料ダウンロードして、ご覧ください!